-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
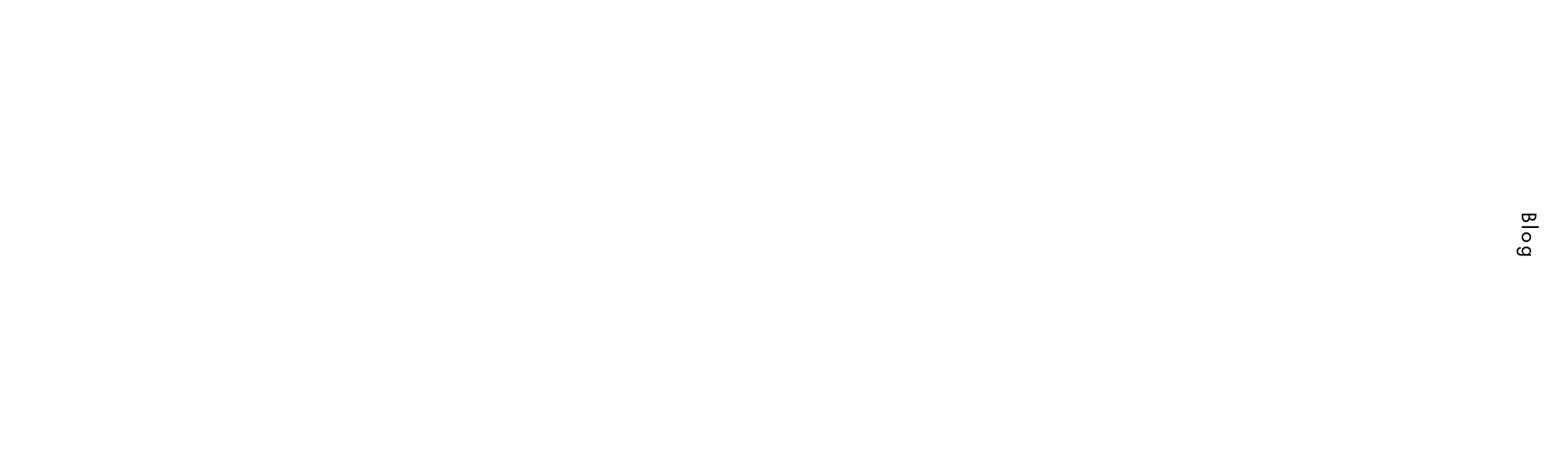
みなさん、こんにちは!
3月といえば、卒業式のシーズン。今回は、誰もが経験する「旅立ちの季節」につい
て、心温まる思い出とともにお話ししていきたいと思います。
卒業式といえば、校歌と仰げば尊しは外せませんよね。特に「仰げば尊し」は明治時
代から歌い継がれてきた曲で、「先生への感謝」という普遍的なメッセージが、時代
を超えて心に響きます。実はこの曲、明治14年に作られた学生唱歌で、当時の師弟関
係の理想を表現しているんです。今でも多くの学校で歌われているのは、その歌詞の
持つ普遍的な価値があるからかもしれませんね。
在校生による「贈る言葉」と卒業生の「答辞」も、毎年感動的なシーンです。何度も
原稿を推敲して、練習を重ねて…。その真剣な姿に、卒業を迎える実感が込み上げ
てきますよね( ;∀;)
卒業アルバムも思い出の宝物。クラスの集合写真、文化祭や体育祭の1ページ1ページ
に、たくさんの思い出が詰まっています。特に先生方の若かりし頃の写真が載ってい
るページは、いつも話題の的になりますよね。最近では、デジタルアルバムやフォト
ムービーを作る学校も増えてきているそうです。
そして卒業式の定番と言えば、アルバムへのメッセージ書き!「部活の思い出」「修
学旅行での出来事」「教室での日常」…。一人一人に向けた言葉を考えながら、こ
れまでの思い出が走馬灯のように蘇ってきます。誰があんなことを書くんだろう?ど
んな言葉を贈ろうか?そんなワクワク感とちょっぴりの切なさが入り混じる時間。最
近はSNSで簡単に連絡が取れる時代ですが、直筆のメッセージには特別な想いが込め
られていますよね。
実は、卒業式の形式も時代とともに少しずつ変化しているんです。従来の形式的な式
典だけでなく、思い出のスライドショーを上映したり、卒業生全員で合唱した
り…。それぞれの学校で、心に残る卒業式を作り上げる工夫がされています。
桜の蕾が膨らみ始める頃、真新しい制服に身を包んだ新入生たちの姿も見かけるよう
になります。新しい環境への期待と不安が入り混じった表情は、私たちの「あの頃」
を思い出させてくれます。入学式での緊張した面持ち、クラス替えの時のドキドキ
感…。春は新しい出会いの季節でもあるんです。
ところで、卒業式の袴姿も素敵ですよね。最近では着付けとヘアメイクにこだわる人
も多く、その準備も卒業式の大切な思い出になっています。友達と一緒に着付け教室
に通ったり、前日にネイルをしたり…。華やかな袴姿は、まさに人生の節目を飾る
にふさわしい装いです(^^)ノ
卒業証書も大切な思い出の品。校長先生から一人ずつ手渡される瞬間、何年もの学校
生活が詰まった重みを感じますよね。証書を胸に抱きながら退場する時の気持ちは、
きっと誰もが覚えているはず。
卒業式が終わった後の教室も、特別な空間です。普段何気なく過ごしていた教室が、
急に懐かしく感じられる不思議な時間。机に刻まれた落書き、窓際の植物、黒板の文
字…。どれもこれも思い出の一部として、心に刻まれていきます。
さて、みなさんの卒業式の思い出はどんなものでしょうか?時が経っても色あせな
い、大切な宝物として心に残っているのではないでしょうか。
あなたの次なる成長の1ページを私たちと作っていきませんか?
いま私たちは一緒に働く仲間を募集しています。ホームページをご覧になって少しで
も興味が湧いたならどうぞお気軽にお問い合わせください。
楽しみにお待ちしています!
みなさん、こんにちは!
2月といえば、バレンタインデー。日本では独自の発展を遂げた、とても興味深い文化になっていますよね。今回は、日本のバレンタイン文化についてご紹介します(^▽^)
日本でバレンタインデーが広まったのは、1950年代後半から。当初は、女性から男性に愛を告白する日として紹介されました。その媒体として選ばれたのが、チョコレート。高級品だった洋菓子のチョコレートは、特別な想いを伝えるのにぴったりだったんです。
面白いのは、この「女性から男性へ」というスタイルは、実は日本独自のもの。欧米では、男女がお互いにプレゼントを贈り合う習慣なんです。この日本式バレンタインは、戦後の日本の社会状況や、百貨店のマーケティング戦略が組み合わさって生まれた、ユニークな文化と言えます。
1970年代には「義理チョコ」という文化も定着。職場の男性同僚や上司に、感謝の気持ちを込めてチョコレートを贈る習慣は、日本ならではのものです。この習慣は、日本特有の「和」を重んじる文化から生まれたとも言われています。
チョコレート文化も、年々進化を遂げています。手作りチョコレートの人気は今も健在。でも最近は、本格的なテンパリングマシンやシリコン型など、プロ仕様の道具も一般向けに販売されるように。SNSでレシピやラッピングのアイデアを共有する人も増えて、手作りの幅がぐっと広がりましたね(*´▽`*)
市販のチョコレートも、すごい進化を遂げています。世界中のカカオ豆を使い分けた本格派チョコや、日本の食材を使った和テイストのチョコ、インスタ映えする見た目の可愛いチョコなど、選択肢が豊富。自分へのご褒美として購入する「自分チョコ」という楽しみ方も定着してきました。
最近では「友チョコ」という形も一般的に。友達同士でチョコレートを交換したり、一緒にチョコ作りを楽しんだり。性別や年齢を問わず、みんなで楽しめるイベントへと広がっています。
職場での義理チョコ文化は、ハラスメントの観点から見直される動きもありますが、かわりに「感謝チョコ」という形で、日頃お世話になっている人へ感謝の気持ちを伝える機会として活用される例も。
また、チョコレート以外のお菓子やグルメギフトを贈る人も増加中。オーガニックスイーツや、食物アレルギーに配慮した商品など、受け取る人の好みや事情に合わせた選択肢が広がっています。
このように、時代とともに形を変えながら、より自由で楽しいイベントへと進化を続けるバレンタインデー。今年は、あなたらしい楽しみ方を見つけてみませんか?(^-^)
みなさん、こんにちは!
12月になると、日本中が慌ただしい雰囲気に包まれますね。「師走」と呼ばれるこの
時期は、一年の締めくくりを告げる、とても特別な月です。師走の伝統と慣習につい
て、今回はお話ししていきたいと思います(^^)/~~~
?「師走」の由来と意味
「師走」という言葉、その由来をご存知でしょうか?もともとは、僧侶(師)が年末
の法要の準備に走り回っていたことから生まれた言葉とされています。一年で最も慌
ただしい月、駆け回る様子を表現した奥深い言葉なんです。
現代では、年末の慌ただしさを象徴する言葉として広く使われています。仕事の締め
くくり、年賀状の準備、年末年始の準備など、実に多くのことが同時進行する月。ま
さに走り回らなければならない、そんな月なのです(´ω`)
?忘年会文化と職場の絆
師走の風物詩といえば、なんといっても「忘年会」。一年の労をねぎらい、同僚や仲
間との絆を深める大切な機会です。古くは江戸時代から続く日本独自の風習で、現代
では企業文化の重要な要素となっています。
お酒を交わしながら、一年の出来事を振り返り、来年への抱負を語り合う。普段は言
えないような感謝の言葉を伝え合える、とても貴重な時間なんです。
?大掃除の意味と精神性
師走の伝統行事といえば、「大掃除」も外せません。これは単なる掃除ではなく、一
年の汚れや穢れを落とし、新しい年を清らかに迎えるための精神的な儀式でもありま
す。
家族全員で家中を隅々まで掃除し、新しい年への準備を整える。この行為には、単な
る衛生管理以上の深い意味が込められているのです。
?年越しそばと家族の絆
大晦日の夜に欠かせないのが「年越しそば」。長く伸びる麺は、長寿や縁の切れるこ
とのない幸せを象徴しています。年の瀬に家族や大切な人と一緒に食べることで、来
年への希望と絆を確かめ合うんです。
?初詣の準備と新年への期待
師走の終わりには、初詣の準備も始まります。新しい年の幸せと健康を祈願する、日
本の伝統的な行事。初詣の準備と並行して、お正月の準備も進みます。鏡餅を飾り、
おせち料理の準備を始める家庭も多いでしょう。
いかがでしたでしょうか?
師走は、一年を締めくくり、新しい年への希望をつなぐ、とても特別な月なんです。
慌ただしさの中にも、深い伝統と文化、そして家族や仲間との絆を感じられる、素晴
らしい季節です。今年最後の月を、日本の伝統と共に、心豊かに過ごしてください
ね。
現在一緒に働く仲間を募集中です!来年はあなたとも、充実した1年を過ごせたこと
を語り合えることを楽しみにしています。お気軽にお問い合わせください。
新しい年への希望を胸に、素敵な師走をお過ごしください!
みなさん、こんにちは!
秋も深まり、スラリとした木々の姿に冬の訪れを感じますね。そんな11月に行われる
日本の重要な伝統行事をご紹介したいと思います。言わずとしれた「七五三」ですね
♪ 3歳、5歳、7歳の男女の子供の成長を祝います。
□■ 七五三の歴史 ■□
七五三の習俗は、なんと1300年以上の歴史を持つと言われ、その起源は平安時代にま
で遡ります。当時、三歳児と七歳児の男女の子供を神社に参拝させ、無事に成長して
くれることを祈願する習慣が広まっていたのです。
やがて、五歳児も加わり「七五三」と呼ばれるようになりました。三・五・七という
“縁起のいい数字”にちなんで、子供たちの健やかな成長を願っているんですね。
明治時代以降は、写真撮影などが加わり、より盛大な行事へと発展。現代では11月15
日が定番の日程となっています。
□■ 七五三の意義 ■□
七五三には大切な意味が込められています。
七五三の由来は、平安時代に行われた、3歳の「髪置き」、5歳の「袴着」、7歳の
「帯解き」の儀式にあるといわれています。 昔は子供の死亡率が非常に高かったた
め、このような節目に成長を祝い、子供の長寿と幸福を祈願しました。 医療が発達
した現代でも、子供を思う親心に変わりはなく、七五三というかたちで受け継がれて
きたのです。
もう一つは、子供の健やかな成長を願うだけでなく、親や家族の愛情を深めること。
髪を整えたり、立派な正装をさせたりと、子供を大切に思う気持ちが表れています。
家族で参拝に訪れ、子供の成長を祝福し合う時間は、絆を確かめ合う良い機会にもな
るのです。
□■ 七五三当日の流れ ■□
さて、そんな七五三当日の様子をのぞいてみましょう。
まず、髪を結ったり、着物を着せたりと、子供を整えていきます。女の子は振袖や小
振袖、男の子は袴姿に身を包みます。こうした正装姿で神社に参拝するのが定番で
す。
参拝では、神職の方から子供たちに祝詞を述べてもらいます。「健やかに育ちますよ
うに」「幸多き人生となりますように」など、子供の未来を祝福する言葉に包まれま
す。
参拝の後は、家族で集まってお祝いムードを盛り上げます。写真撮影をしたり、記念
の品物をプレゼントしたり。おいしい料理を囲んで、楽しい一時を過ごすのが恒例で
す。
□■ 近年の七五三事情 ■□
最近では、SNSの普及によって七五三の楽しみ方も変化してきました。
写真撮影にはまる家庭が増え、インスタ映えする可愛らしいコーディネートを楽しむ
子供たちも。美しい着物姿を撮影し、オンラインで共有するのが新しい七五三の楽し
み方なのです。
また、行事の意義を大切にしつつ、より個性的な演出を凝らす家庭も。お気に入りの
小物を身につけたり、ユニークなロケーションで撮影したりと、子供らしさをより引
き出すアイデアが広がっています。
このように、時代とともに変化を遂げつつも、七五三にはいまなお健やかな成長を祝
福し、家族の絆を深める大切な意味が息づいているのです。
11月15日、この伝統行事を通して、日本の歴史と文化を感じてみてはいかがでしょう
か?
子供たちの笑顔に心が和むこと間違いなしです♪
□■ 私たちの会社で働いてみませんか? ■□
可愛い子どもの健やな成長を見守り、節目を祝うには、親としても充実した毎日を過
ごしていたいですね。
そのためにはやりがいのある仕事を持つことも大切です。私たちの会社で働いてみま
せんか?
毎日を充実して過ごすためのやりがいを用意してお待ちしています!
みなさん、こんにちは!
五月晴れの心地よい季節となりました。
さて、タイトル通り、5月は〇〇〇月間といわれていますが、なにかご存知でしょうか?
5月30日は「消費者の日」です。1978年、日本政府によって制定されました。1968年5月30日に「消費者保護基本法」が公布・施行された出来事にちなんで「消費者の日」とされ、その10周年となる1978年に、正式な記念日として決定しました。
そう、5月は「消費者月間」というわけです。
5月1日~31日の1ヵ月間を「消費者月間」とし、啓発運動を実施。消費者の権利を守り、被害を防止することがおもな目的です。
毎年テーマが決められており、今年は「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。
デジタル化やAI等の技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく速くなる中で、わたしたち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化しています。
そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、求められる「消費者力」とは何かを考え、高める機会となるように、このテーマが制定されたそうです。
インターネット通販での意図しないサブスクリプション購入や、ゲームアプリ等での子どもの高額課金、SNSで知り合った人や広告をきっかけとした投資詐欺など、デジタル時代における消費者トラブルは年々増え続けています。
「自分は大丈夫」と思わず、なにか契約をする時には一歩立ち止まって考えることを大切にしたいですね。
デジタルの普及によって、マーケティングの世界でも大きく変わったことがあります。
それは、「サーチ」と「シェア」が爆発的に増加したことです。簡単にお店の情報を検索することができるようになり、メニューや外観といった「サーチ」だけでなく、その店に足を運んだ人々がお店の評価を「シェア」し、それを様々な人が見られるようになりました。
「シェア」については、口コミサイトだけでなく多岐にわたるSNSで可能となり、「サーチ」もホームページだけでなく、誰かが投稿したSNSを見ることが増えてきています。
お客様側の「シェア」をもとに、今後より良いサービスを提供するにはどうしたらいいか、私たちは考えることができるようになってきたわけです。
そういうわけで、いつもお客様の声を届けてくださるみなさんには感謝しています。
これからもより良いサービスをお届けできるよう、精一杯努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします!
みなさん、こんにちは。
いよいよ春にさしかかるこの季節、まだまだ寒い日もありますが、いかがお過ごしで
しょうか。春を彩る桜の花が、そろそろそのつぼみを開こうとしています。
さて、桜の花が咲くころといえば、卒園式・卒業式の時期ですね!
ご卒業後、進路にはさまざまな選択肢がありますが、その一つに「働く」ということ
があると思います。みなさんは、働くということにどんなイメージを持っています
か?
「大変そう……」「やりがいのある作業」「お金を稼ぐ手段」など、さまざまな印象
があることでしょう。せっかく仕事をするのであれば、より楽しく、より精力的にな
れるような職を探せるといいですね!
それには、職種だけでなく、職場の環境も見る必要があります。どんなに自分の好き
な仕事であっても、同僚や上司との関係が悪ければ、苦痛を伴う職場になってしまう
可能性があるからです。
弊社では、一緒に仕事をするお互いのことを仲間だと思っており、休憩時間にはお互
いのことを話すこともあります。もちろん、プライベートなことを無理に詮索すると
いったことはありません。親しみやすい仲間たちと話して距離を縮め、楽しい職場環
境を作りながら、自分の仕事に精を出してみませんか?
現在、弊社では求人を募集しております!お気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしております(*^^)v
こんにちは。
立春を迎えましたが、まだまだ冬の厳しい寒さが続きますね。みなさまいかがお過ご
しでしょうか?
この時期は乾燥している日も多く、肌の乾燥や手荒れといった困りごとに悩んでい
らっしゃる方が多いのではないでしょうか。市販のハンドクリームや手袋などを駆使
して、この季節を乗り越えている人も多いことでしょう。
仕事をする際、手荒れがひどいとストレスになりますよね。
感染症対策で手洗いや手指消毒は日々欠かせないものとなっている昨今、その方法を
少し見直してみる必要があるかもしれません。こまめに手洗いを行うことは大切です
が、あまりにその回数が多いと、手の皮脂が取り除かれやすくなってしまい、手の乾
燥に繋がります。
特に、この寒い季節には意外とやってしまいがちなのですが、お湯で手を洗うこと
は、うるおいを肌から奪ってしまう大きな要因です。温かい水を使いたい気持ちはあ
りつつも、なるべく避けられたらいいですね(笑)
また、手を洗った後は、ハンドソープをしっかり流しきり、手をふくようにしましょ
う。洗い流しきれていなかったり、水滴が手に残ったままにしたりすると、手荒れの
原因になりますよ。
他にも、手肌にやさしいハンドソープを選んだり、手指の消毒で自分に合った保湿剤
が含まれたものを使用したりすることで、肌荒れを回避することができます。仕事で
ストレスを増やさないためにも、日々の手洗いから意識してみるとよいかもしれませ
ん。
さて、このように、日々の小さなことから見直してみるのは、今後もっと元気に仕事
をしていくうえで大切なことだと思います。もちろん、仕事上のルールを再度確認し
たり、より効率の良くなる仕事の仕方を模索したりするのも大切ですが、小さな見直
しはなにも仕事上に限ったことではありません。日々の暮らしの中で、仕事にストレ
スを持ち込まないために手荒れ対策をしたり、元気な身体で出勤できるように夜ぐっ
すり眠ったり、自身の生活を見直していけるところはきっとたくさんあります。
職場の人間関係も同じで、日々挨拶をし、たまに雑談をし、楽しい雰囲気を作れる職
場であれば、休憩時間だけでなく仕事中も明るい気持ちで勤務に臨めるのではないで
しょうか?
弊社では、毎日のちょっとした挨拶から始める、明るい職場づくりに励んでいます!
今日も一日仕事に精を出すために、皆が声を掛け合い、力を合わせています。ともに
切磋琢磨しながら働いてみませんか?
求人大募集中です!お気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしております(*^^)v
突然ですが、
12月といえば、クリスマス!
――と思い浮かべる方は多いと思いますが、それでは12月23日は何の日かご存知で
しょうか…?
改めまして、みなさんこんにちは。
急に冷え込む日が増え、いよいよ本格的な冬の訪れを感じられる頃になりました。慌
ててコート類を用意した方も多いかもしれません。衣類だけでなく、身体を芯から温
めてくれるお野菜なども身体に取り込んで、風邪をひかないように気を付けてくださ
いね。
さて、みなさんは12月23日といえば何の日かご存知でしょうか?
クリスマスツリーよりもずいぶんと高い、あのタワーの完成日です・・・
そう、333mの高さを誇る「東京タワー」の完工式が執り行われた日となっています!
東京タワーの設計は「塔博士」とも称される、日本の塔設計の第一人者である構造
家・内藤多仲らによって行われ、総工費は約30億円、完成までに約1年半の歳月がか
かったといわれています。
では、そんな膨大な金額や時間をかけてまで、なぜ東京タワーは作られたのでしょ
う?
1953年には NHK が日本初となるテレビ本放送に成功し、その後次々と地方の放送局
が電波を発信できるようになります。しかし、その時には電波塔というものが存在し
なかったため、各局は独自のアンテナを使い電波を発信していました。各局がそれぞ
れ電波を飛ばすのは効率が悪く品質の良いものではありませんでした。
当時日本は高度経済成長期。「全てをまかなう電波塔を作ろう!」という理想の元、
日本一高い建築物を目指して東京タワーが作られたそうです。
今では日本の立派な観光名所として名高い東京タワーですが、実はそのような発想で
実用的な背景に基づいて作られたのだと思うとなんだか感慨深いですね。東京タワー
のおかげで、私たちはテレビを自由に楽しめているといっても過言ではありません
(?)
12月23日は東京タワーの日。
もしまだ登ったことがない方は、この機会に一度登ってみるのもオススメです。地上
約150mにある、メインデッキの大展望台では、東京の景色を一望することができます
よ♪この時期は寒くておうちにこもりがちですが、たまにはお出かけしてみるのもい
いかもしれません(´艸`*)
風邪をひかないようにコートなどを着込んで、おしゃれをして、冬のお出かけを楽し
んでください!
みなさん、こんにちは!本格的に涼しい秋の風が吹き始め、「〇〇の秋」を楽しみや
すい時期となってきましたが、いかがおすごしでしょうか?
一番はやはり「食欲の秋」でしょうか。栗ご飯や秋刀魚の塩焼き、松茸のお吸い物な
ど、旬の食べ物を使った料理がメニューにも増えてきた頃かと思います。
「スポーツの秋」ということで、運動しやすい気温と湿度のこの季節には、運動会が
開催される学校も数多くあります。お散歩日和な日々も多くカメラを持ってお出かけ
するのも楽しそうですね。
ほかにも「読書の秋」といったものがあります。図書館で本を借りたり、喫茶店で
コーヒーを飲みながら愛読書を楽しんだりできる季節です。また、「〇〇の秋」では
ありませんが、10月31日にはハロウィンもあって、どこか浮足立つ雰囲気が街中に感
じられるのもこの時期の特徴ですね。
さて、そんなイベントが盛りだくさんな10月ですが、みなさん、10月14日は何の日か
ご存知でしょうか?
あまり知られていないかもしれませんが、10月14日は「鉄道の日」です。
1872年10月14日に、新橋と横浜を結んだ日本初の鉄道が開業しました。「鉄道の日」
の歴史は長く、1922年に鉄道省から、鉄道が国民に広く愛され、その役割についての
理解と関心がより深まることを願って「鉄道記念日」が制定されました。
なお今年は、「鉄道の日」が制定されて30周年を迎えるおめでたい年でもありま
す。いまや多くの都市で必須ともいえる交通機関である鉄道が、明治時代に開通した
ばかりと考えると少し驚きですねΣ(・ω・ノ)ノ!!
「鉄道の日」にちなんで、鉄道の写真展や、鉄道に関する俳句コンテストといったも
のが開催されています。この機会に普段よく乗る鉄道の歴史について調べてみたり、
秋を走る鉄道の写真を撮ってみたりしてみてはいかがでしょうか?
秋の風が気持ちよく、鉄道散歩をするのにもうってつけなこの季節。家族や友達、大
切な人と一緒に、「鉄道の秋」を楽しんでみませんか?
10月はイベントが盛りだくさんで、楽しい月になりそうですが、急に肌寒くなってく
る季節でもあります。お身体には十分気を付けて、素敵な秋をお楽しみくださいね。
みなさんが楽しんだ秋の時間を、ぜひ私たちにも教えていただれば嬉しいです♪
そろそろ秋の風が吹いてくる季節となりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
9月といえばお月見、そして月が一番きれいに見える「中秋の名月」があります。
今年の「中秋の名月」は、9月29日です。19時ごろから21時ごろまでが見ごろとなっています。空模様だけが心配ですが、晴れていれば、涼しい秋の風が吹くおかげで湿気が少ないため、くっきりとした綺麗な満月を見ることができるでしょう。
「中秋の名月」で見られる満月は、一年の中でもっとも美しい月とされ、みんなでお月見をする風習があります。残暑が去ってお外にいるのも心地よい時期。ご家族や大切な人と一緒に四季を感じる行事としても、お月見はおすすめです。
では、私たちがおススメするお月見の楽しみ方を2つご紹介しますね♪
ひとつは、「月見団子」をご家族で作ってみることです。
お子さんのいるご家庭であれば、特に楽しめるかと思います。子どもでも比較的作りやすいのが月見団子。お団子の形は地域によって変わるといわれていますが、ご家庭それぞれ、いろいろな形の団子を作ってみると面白いでしょう。きな粉やみたらし、あんこを添えて、美味しく頂いてください!
親子でお団子を一緒に作る機会もそうそうありません。お月見になぞらえて、せっかくの機会、素敵な思い出ができると良いですね。
もうひとつは、少し大人の嗜み方ですが、お外で日本酒を嗜むという楽しみ方です。
おうちの縁側で満月を見ながら嗜むも良し、眺めの良いレストランで少し高級なものを嗜むも良し、お外の立ち飲み屋で仕事仲間と共にワイワイしながら日本酒を嗜むも良し、どれも素敵なお月見になること間違いありません。
お月見に日本酒という組み合わせは、「月見酒」そのものです。ちなみに日本では、「月見酒の日」というのも制定されています。気になる方は調べてみてくださいね。「得月」や「雨後の月」、「夜半の月」など、月の名前が入った日本酒は、月見酒にもぴったりですよ。
というわけで、今回は「中秋の名月」をより楽しむ方法についてご紹介してみました。一年でもっとも美しいとされる満月、ぜひ見逃さないようにしてくださいね!
それではみなさま、素敵な満月の夜をお過ごしください(*^^)v